これから公開 映画の地球 『ル・コルビュジェとアイリーン ~追憶のヴィラ』メアリー・マクガキアン監督
『ル・コルビュジェとアイリーン ~追憶のヴィラ』メアリー・マクガキアン監督

映画の地球 ラテンアメリカの映画 10 プエルトリコの独立問題を扱った映画『テロリストを撃て!』
プエルトリコの独立問題を扱った映画『テロリストを撃て!』
プエルトリコの“良心の囚人”オスカル・ロペスのことを先日、書いた。大半の読者がロペスの存在を知らなかった。
ラテン音楽ファンには、リッキー・マルティンを筆頭にたちまち両手の指がおれるほどの歌手を数えることができるだろう。往年のラテン音楽ファンならトリオ・ロス・パンチョスの創設メンバーにプエルトリコ出身者がいたことを想い出すかも知れないが、プエルトリコの政治となるとまったくの白紙といって良いだろう。
数日後にノーベル平和賞の発表があるが、ロペスが受賞してもおかしくない。たぶん、候補者の一覧表に彼の名前も記載されているのだろう。
ロペスのことを書いたり調べたりしている頃、プエルトリコの債務問題は緊急課題として俎上していた。そして、原稿が活字になるころには事実上のディフォルト(債務不履行)に陥った。米国にとっては地方自治政府の経済破綻となるが、財政援助を行なうことはないだろう。かつて自動車の“都”デトロイトが破産したときも連邦政府は助言はしたが救済措置はとらなかった。プエルトリコが州ではなく自治領であるため連邦破産法は適用されないから問題は深刻だ。そして、プエルトリコの独立派は、この経済危機という“好機”を利用して、その声を高くすることもできない。何故なら独立はさらなる経済負担を強いることになるのは明白だから、おいそれとはできない。独立しても、債務を支払う義務は消えないからだ。カリブの小国ハイチは、独立 と引き換えに巨額の債務をフランスに支払いつづけ、今世紀まで最貧国の汚名を強いられた。革命ロシア政府はロマノフ帝政時代の債務を西側諸国に返済しつづけていた。確実にいえることは、米国本土への出稼ぎ者がさらに増大するということだろう。観光も、キューバが米国と国交正常化の道を進むなかでビジネス規模は縮小していくだろうから、先行きは不透明だ。
プエルトリコの経済問題を課題にするつもりはなかった。ここで書きたいのは、ロペスが活動していた時代のプエルトリコを描いた映画がアメリカで制作されているので、それを紹介することである。
プエルトリコを舞台にした映画や、プエルトリコで制作された映画というのはけっこうあるが日本ではほとんど黙殺、というか関心をもたれない。
数年前、ジョニー・デップ主演の『ラム・ダイアリー』という佳作があった。1960年代のプエルトリコを描いた映画で、デップは実在した新聞記者を演じた。プエルトリコの自然環境を破壊する米国企業の経済進出を糾弾した社会派作品だったが、これだってデップが主演していなければ日本で公開されることはなかっただろう、という映画だ。
スペイン市民戦争後、共和派の人びと、そのシンパの多くがラテンアメリカ各地に亡命した。プエルトリコにもやってきた。市民戦争の勃発期にフランコ王党派に暗殺された詩人ガルシア・ロルカを描いた映画が、プエルトリコに亡命した両親のもとで育った青年の視点から撮られている。この日本公開も知名度のたかい詩人の物語だったから実現したのだろう。米国映画ではなくプエルトリコ映画として公開された。制作資金をプエルトリコの経済界が提供していたが、今回のディフォルトの影響をどれだけ受けただろうか。
そして、もう一遍の映画がここにある。『テロリストを撃て!』。劇場公開はされなかったがVHSでは発売された。むろん日本ではDVD化されることはないだろう、とおもって急遽、紹介する気になった。オスカル・ロペスを理解する資料になるとおもったからだ。
1978年、プエルトリコ自治領制定記念式典の最中、独立を志向する3人の過激派が放送塔(プエルトリコでは「東京タワー」的存在)を襲撃・・・しかし、それは罠で、待ち伏せする警察隊によって過激派の2人が射殺される、という事件が起きた。
この事件は、やがて現状維持派ないしは米国の州昇格を志向する自治州知事を再選させることになる。しかし、その仕組まれた“事件”は女性TVレポーター(エイミー・アーヴィング)の活動によって真相が暴かれてゆく。米国映画だが、立場は、明白に穏健独立派、ないしは自治州での権限を独立国なみに高めようと志向する立場に傾斜している。
製作・脚本は米国人だが、監督はブラジルのブルーノ・パレット。本作の7年後、軍事独裁下のブラジルで起きたリオ・デ・ジャネイロ駐在の米国大使が過激派に誘拐された事件を取り上げた『クワトロ・ディアス』や、さらに日本でも評判になったリオのスラム街の少年ギャングたちの生と死を東映やくざ映画全盛期の深作欣二監督ばりの実録タッチで描いた『シティ・オブ・マッド』などを撮る才能だ。
プエルトリコ事情が日本ではよく知られていないということで、劇場公開はなくVHSでの発売となったが、冷戦下のカリブ圏でキューバに近いプエルトリコに浸透するキューバの影響というものに米国、ないしはFBIは神経を尖らせていたか、といったことがよく伝わってくる映画だ。レポーターの上司に名優ロバート・デュパル、主都サン・ファンでFBIのエージェントとして働く、映画では悪役となる男に『ラ・バンバ』などチカーノ役をさまざまなキャラクターで演じきっているルー・ダイアモンド、そして人権派のプエルトリコ検察官にアンディ・ガルシアなどが配されている作品だから、常識的に考えてもB級映画ではありえない。つまり、米国でも1978年の事件は関心事の高いものだったということだ。
その事件の文脈のなかでオスカル・ロペスたちの活動があるのだ。ということを知ってもらいたいために敢えてVHS版しかない『テロリストを撃て!』を記録しておきたいと思った。(原題 A SHOW OF FORCE) 2015-10記
映画の地球 ラテンアメリカの映画 9 薄汚れたグリンゴを演じたジョニー・デップ 米国自治領プエルトリコへの問い 映画『ラム・ダイアリー』 ブルース・ロビンソン監督
映画『ラム・ダイアリー』 ブルース・ロビンソン監督  プエルトリコでラム酒に浸りきった日々を過ごす情けなくも薄汚れたジャーナリストの端くれ男ポール・ケンプ(ジョニー・デップ)の蘇生物語。
プエルトリコでラム酒に浸りきった日々を過ごす情けなくも薄汚れたジャーナリストの端くれ男ポール・ケンプ(ジョニー・デップ)の蘇生物語。
今日のプエルトリコ自治政府は破産政府である。ワシントン政府の補助がなければやっていけないカリブの島国だが、ここには米国からの独立を願望する島民が少なからず存在する。そして、独立はしたいが、米国の自治領であることによって経済的恩恵を受けていると信じる現実派が島民の過半数を占め、米国への融合、州となること拒み自治領という地位を選んでいる。
映画に描かれる時代は1960年、若きジョン・F・ケネディが、ニクソン候補を退けて米国大統領に当選した年だ。プエルトリコはといえば保守派のムニョス知事が米国領自治領の主として座っていた時代。1952年、米国は、「プエルトリコを植民地支配している」という世界的批判をかわすため自治権を与えた。冷戦下、米国は足元を固めるために米州機構(OCS)の結束を高める必要から、域内諸国の批判をかわすために自治権を与えたのだ。物語は自治領となって8年目の首都サンファンを舞台に進行する。
ムニョス知事は米国本土から企業を誘致、工業化を進めたがインフラの未熟な地ではなかなか根付かず、結局、カリブの美しい浜を米国資本のリゾート地として開発し、観光客を誘致、手っ取り早く稼ぐ方向に流れる。土地は収奪され、農漁村で立ちゆかなくなった島民は米国領市民として、職を求めてフロリダやニューヨークに渡っていった。ミュージカルの古典『ウエスト・サイド物語』はそんな時代の貧しいプエルトリコ・コミュニティーの話だった。
デップが演じる駆け出しの新聞記者ポールは実在の人物。本国で食い詰めた作家志望の青年が、サンファンのローカル英語紙の記者となって、なんとか喰い次ぎ、やがて小説を世に問いたいと夢想している。しかし、くだんの編集部はまったく覇気がない。新聞は売れず、米国資本の企業の広告収入でやっと経営を維持する、いわゆる“御用新聞“。米国資本の工場が、汚染水を海に垂れ流している事実を知っても記事にはできない。そういうたぐいの新聞だ。
倦怠と頽廃が重いオリとなってはびこり腐臭をただよわせている。そうした編集部の光景、ポールの仮寓先の場面などはいずれも色調暗く不快な感じを与える。それに反して浜の美しいこと、緑の鮮やかなこと、澄んだ大気の拡がりは素晴らしい。対比があざやかだ。つまり米国人が登場する場面は暗く、プエルトリコの自然は湿度のあかるいハイトーンの色調となる。
デップに与えられた役は、そうした頽廃の気配のなか、どうにか初心を忘れず平衡感覚維持し、米国資本の不正を暴く記事を書きジャーナリストとしてのプライドを保ちたいというものだが、結局、それも果たせず本土へ撤退するというていたらく。しかし、その反ヒーロー的な主人公こそ、ラテン諸国でのグリンゴのいやらしさ、あくどさ、浅ましさを体現するものだ、と描かれている。デップはそんな米国人のいやらしさを好演する。
「パイレーツ・カリビアン」などでかっこいいデップを見なれたファンにはあんまり見たくない姿だろう。そうカリブ海はコロンブス以来、無法者たちの荒稼ぎの場であった。武勇のパイレーツも所詮、海賊、泥棒、人殺しだ。その泥棒たちは、やがて巧妙に自己保身を謀り、ビジネススーツをスキなく着こなし、パソコンのキーを叩きながら海賊以上に収奪しているのが今日的光景なのだ。
美しい浜を開発しようと米国人たちが下見するシーンがある。その後背地に米軍の射爆場があって、空気を切り裂いて砲弾が飛び交っている。そう、プエルトリコは中米パナマの広大な米軍基地を失った現在、ラテンアメリカにおける最大の米軍演習場になった。この小さな島国は、その美しい自然とともに沖縄とよく対比される。そして、ともに地に根を張った民衆の反基地闘争が存在する。プエルトリコの群衆が“御用新聞”の社屋にデモを仕掛けてくるシーンなどもちゃんと用意されていて、それなりの時事的臨場感も創られている。この自治領の矛盾を知るにはよき資料かも知れない。
*プエルトリコは米国自治領であるが、民族文化はラテンアメリカに連動する。住民の大半はいまでもカトリック信徒は過半数を占める。そして、経済的な実益を考慮しなければ、住民は米国からの独立を目指すという意味で、「ラテンアメリカの映画」のカテゴリーで語りたいと思った。
2011年制作・米国映画
映画の地球 プーチン独裁したのロシア映画 5 t.A.T.uのポップスをBGMにしたチェチェン紛争映画『厳戒武装指令
t.A.T.uのポップスをBGMにしたチェチェン紛争映画『厳戒武装指令』ニコライ・スタンブラ監督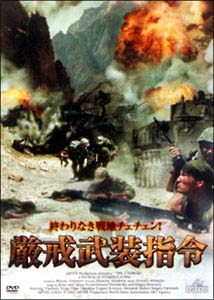 冷戦末期、ソ連はアフガニスタンに介入して混迷し、共産党独裁の崩壊に繋がった。
冷戦末期、ソ連はアフガニスタンに介入して混迷し、共産党独裁の崩壊に繋がった。
アフガニスタンの親ソ派政権を維持するための武力介入は、ソ連を疲弊させた。
タタール人の侵入、ナポレオンのモスクワ占領、ナチ・ドイツ軍の侵攻に対する戦いは基本的に平原での戦いであった。勇猛果敢なコサック兵も平原での騎馬戦に長けていた。しかし、アフガンでの戦いは、険しい山岳地帯の地勢をよくしるゲリラ戦のなかで苦闘した。
ソ連軍には山岳地帯での戦いに対する教典はあっただろうが、実戦から学ぶことは少なかった。ソ連圏を大戦後、ほどなく離脱したチトー大統領のユーゴスラビアにソ連が介入できなかったのも、地上戦では山岳戦に長けたチトー軍との戦いをい避けたからだ。
アフガンの戦いでソ連軍は確かに学んだ。多くの若い兵士たちが血と肉を飛散させて山岳戦の要諦を学んだのだ。代償はあまりにも大きかった。甚大な兵士の死は、やがてソ連そのものを崩壊させたのだ。
いま、中央アジア諸国の墓地を訪れると、アフガン戦争で戦死した若い兵士たちの墓標が林立しているのをみることができる。彼らの墓標を確かめるために訪問したわけではないが、中央アジア諸国に散在する大きな墓地にはたいてい日本将兵の共同墓地があり、その墓参に訪問すると、そこに若い青年像を墓碑に複写した墓が林立して目につくのだ。
日本将兵の墓とはいうまでもなくシベリア抑留時代の強制労働で亡くなった無念・無慚と望郷の涙のなかで病み、あるいは飢えのなかで死んでいった人たちの墓である。近くへいけば、それに手を合わせるのは日本人の義務と思う。
一度、ウズベキスタンの首都タシケント郊外の墓地で、日本の墓参ツアーに出会ったことがある。先日、安倍首相が詣でた墓地だ。
その墓地には日本将兵とおなじように抑留生活で命を落としたドイツ軍将兵の墓がある。アフガン戦争で命を落とした若い兵士の墓もある。けれど、ドイツ軍将兵の墓に目を留める日本人はいないし、また阿部首相も気がつかなかっただろう。ましてやアフガン戦争で戦死した若者の墓など一顧だにされない。そういう安倍首相の姿、日本人墓参団の行動を地元のひとたちは注意深くみていることを忘れてはならない。
中央アジアのイスラム国から多くの若者がアフガンの戦場に狩り出された。戦場まで近いということ、同じような風土に生活していること、そしてアフガンのタジク語に通じている者が多いことも理由だった。
しかし、ハリウッドがベトナム戦争の矛盾、非人道性を早くから映画化したようにはソ連のモスクワとレニングラード(現在サクトス・ペテルブルグ)の二大撮影所はアフガンの負け戦を撮らなかった。
共産党独裁下ではいうまでもなく表現の自由は封殺され、負け戦さを描くなどもってのほか、という時代だった。映画人は沈黙していた。それがソ連映画界だった。
しかし、チェチェン戦争では早くから映画が撮られた。政府に批判的な視点からも撮られている。
アフガン戦争のように封印するのではなく、チェチェン独立過激派のテロを描くことによって、戦争の正当性を訴えられるとおもっているのかも知れない。前に取り上げた『大統領のカウントダウン』などは、その典型だろう。
〈チェチェン〉はロシア映画に繰り返し描かれることになる。ベトナムが米国人の最大の関心事になったように、〈チェチェン〉はロシアの安全・平和を語る際のキーワードになったからだ。
ソ連時代、欧米はもとより日本でも〈チェチェン〉を知るものはなかったが、ソ連崩壊後、にわかにロシアでもっとも有名は自治共和国として浮上した。その内戦の苛烈で・・・。
だから、〈チェチェン〉を記号としてロシア映画を観ていくとプーチン政権下での表現の自由、検閲の許容度が理解できる。あるいは、チェチェンに対する政策の変化、あるいは連邦内の少数民族に対する政策の変容もなんとなくわかってくる。
チェチェンの戦場では、かつてアフガンで戦友だったロシア人とチェチェン人が死闘を交えるということになった。そんなエピソードが語られるのが本作である映画に(2002*原題「前進 突撃」 )があった。日本では劇場未公開ままでVHS、そしてDVDでの発売となったため知る人が少なし、まともな批評は日本で書かれなかった。一部、戦争映画おたくがB級アクション扱いで紹介していたぐらいだろう。この映画はまず、プーチンが第2代ロシア大統領に就任して3年目に入った時期に制作されている。
ロシア軍に徴兵され空挺部隊に志願した孤児院出身の主人公サーシャのチェチェンでの戦いが縦軸として流れ、そのあいだに幾つかの挿話が挟み込まれ、ロシア現代史の歪みが垣間見えるという仕掛けだ。サーシャの戦争という視点からだけみればB級戦争アクションとなるが、むしろ、挿話のほうが興味深いのだ。
たとえば、映画にアフガンの戦地で同じ釜の飯を食った旧ソ連軍兵士がいま、チェチェンの戦場で敵対しているという現実がある。ソ連軍がアフガンから完全撤退を完了したのが1989年。その5年後には第一次チェチェン紛争がはじまっている。ソ連崩壊直後、エリツィン大統領の時代だ。若き兵士時代、アフガンで戦友だった男たちが、数年後にチェチェンで敵同士となるのはきつい現実だろうし、それは悲劇だ。実際にそんなことはあったはずだ。
映画はチェチェン人の武装勢力を決して唾棄すべき存在としては描いていない。むしろ、チェチェンの混乱に乗じて入ってきた外国籍のイスラム過激派組織の存在を指弾している。
また、サーシャの戦友ウラジミールがチェチェン武装勢力に捕獲された後、脱走中の戦闘で戦死するのだが、その父親が息子の安否を案じて、ふと過去を振り返るシーンがある。
「チェコスロヴァキアの動乱を国は、社会主義を崩壊させようとする帝国主義の陰謀だと教えられ、チェコ人を武力弾圧した。しかし、それはチェコの民主化運動を潰したことだったことを後で知った」と。
それを聞かされるウラジミールの妹は、「チェコではそんなことがあったの」と世代間の位相が象徴される。
海外に出てゆく映画で、ロシアがチェコでの“犯罪”を認めた例は少なくとも筆者にははじめて知る。
チェチェンでの戦闘を描きながら、ウラジミールの妹、その友人たちが享受する青春は、t.A.T.uのポップスをBGMにして描かれる。それもまたロシアの現実であった。
映画の地球 ラテンアメリカの映画 8 映画『ボーダータウン ~報道されない殺人者』グレゴリー・ナバ監督
映画『ボーダータウン ~報道されない殺人者』グレゴリー・ナバ監督
米国の最南端、メキシコ最北端がせめぎ合うところ、そこはボーダー、国境だ。3141キロにおよぶ長大な距離だ。
ちょっと想像できない距離だと思うが、日本列島をまず思い浮かべていただきたい。北海道の北の端・稚内から直線距離で確か台湾に届く、いや縦断してしまう距離であったと思う。そして、そこは世界最大の富裕国USAと、一握りのとてつもない資産家と膨大な数の貧困者が住むメキシコが接する場所である。経済的矛盾が牙をむき出して拮抗している場所だ。
映画はその経済格差が生み出したマキラドーラの工場ではたらく未熟練の低賃金労働の女工さんたちを襲う惨劇が主題だ。マキラドーラとは労働現場の治外法権、メキシコであってメキシコの国内法が発動されない地帯といえる。だから、経営者側はいってみれば、やりたい放題となる。
資本は米国や西欧諸国、そして日本や韓国など先進諸国の大企業だが、労働力はメキシコの廉価であり余っている地方出の若い労働者。国境の南側に立ち並ぶ工場では家電製品が生産され米国で大量消費される。米国の快適な暮らしを演出する電化製品は、劣悪な労働現場で生産されているものだ。
まず、労働組合もなれけば社会保障も完備しているとはいいがたい。雇用側は労働者を使い捨てとしか思っていない……というブラックな部分はこの映画では真正面から扱われていないが示唆はされている。雇用側は女工さんをロボットより使い勝手の良い“機械”としてしかみていなのではないか。つまり彼女たちの生命を軽視される。
そんな労働風土のなかで連続して起きているのが、女工さんたちを標的としたレイプ殺害事件だ。
メキシコ側のフォレスで頻発し、その犠牲者はメキシコ警察の発表では約500件。それだけでもすさまじい数だが、警察当局の意識的怠慢は憎むべき犯罪を放置していると言わざる得ない。犠牲者の実数は闇に葬られ、人権組織などによれば5000件を超えるというのである。警察が認めた数の10倍であり、いまも犯罪は消えていない。
この事件の真相をレポートしようと米国からやってくるローレン(ジェニファー・ロペス)と、地元で事件を追う新聞記者ディアス(アントニオ・バンデラス)に、レイプされ九死に一生を得たメキシコ・オアハカ州出身の若い先住民女性エバ(マヤ・サパタ)が絡んで犯人たちを追及・告発するというサスペンス仕立ての映画だが、硬派のナヴァ監督の意図は社会告発であることは明白だ。南北の経済格差であり、資本の悪辣というものだろう。デビュー作の『エル・ノルテ』以来、『ラ・ファミリア』、『セレナ』とラテンアメリカ諸国の移民・難民、経済問題を米国ヒスパニック社会のなかから発信しつづけたナバ監督がマキラドーラを背景とする一連の殺人事件に無関心でいられなかったのは当然だろう。
また、本誌の読者ならナヴァ監督がスクリーンを通してチカーノ音楽、さらにラテンアメリカ音楽の現況を伝える役目すら担ってきたことも知るだろう。
ジェニファー・ロペスが歌手として本格的な活動を展開するきっかけとなったのはテハーノ・ポップスの女王セレーナの悲劇的な生涯を描いた『セレーナ』に主演したことがきっかけだった。彼女は、その前に『ミ・ファミリア』でメキシコ先住民出身の女性役を演じている。本作にもコロンビア出身で、撮影当時、ラテン世界のアイドルのひとりであった人気歌手ファネスが登場し、ヒット曲をマフィアの内輪のパーティーで歌うという場面がある。そのステージをみてエバが狂喜するシーンがあって、それは役というよりマヤ・サパタの感激そのものを刻印しているようで面白かった。
ジェニファー・ロペスが演じるローレンはメキシコの不法越境者の子という来歴を封印しキャリアを積もうとしているジャーナリストである。そんな彼女が何故、米国でも有数の新聞社に勤めることができたかというディテールは完全に削られている。ナバ映画ではそういうそぎ落としが良くある。そんなローレンは女工のエバと行動をともにするなかで、越境に失敗していれば自分もマキラドーラで働いていたかも知れないし、レイプされ殺される可能性すらあった、と思う。それはすこぶる現実的な想像だ。エバを演じたマヤ・サパタは日本での公開はないが、メキシコではヒットした青春映画などでおなじみの新進女優で、映画は彼女を採用することでメキシコでの注目されることを計算しているだろうし、連続殺人事件への関心を促していることは確かだ。
ナバ監督は、一連の事件を大局的にマキラドーラの矛盾に満ちた搾取構造に起因すると語っているように思うのだが、ではなぜレイプされ、ときに猟奇的に殺害されるという犯罪の闇は解明されない。メキシコにはこの事件をめぐってさまざまな噂が渦巻いているといってよいだろう。そのなかには惨酷、おぞましいものまである。映画はそれはまったく語っていない。そのおぞましさは今日、メキシコにおける麻薬戦争による犠牲者の姿に通底するものがあるが、いまははっきりと確証があるわけではないので書けない。しかし、メキシコではしきりにうわさされている凄惨きわまりないものなのだ。
制作前、撮影中にもスタッフは脅迫を受けていたといわれるが、その圧力によって、糾弾の矛先がすこし鈍磨したのかも知れない。 2008/9記
映画の地球 アフリカを描く 4 セネガル*映画『サンバ』エリック・トレダノ監督 移民問題は先進国の映画に潤沢な滋養を与えている
移民問題は先進国の映画に潤沢な滋養を与えている
映画『サンバ』エリック・トレダノ監督
ルーブル美術館やエッフェル塔周辺……外国人観光客が行き交うパリ界隈、ひとめでアフリカ系と判る男たちが、見栄えもせず造作もぞんざいな真鍮製のエッフェル塔のミニチュアをむき出しにして観光客に売っている。きょうび、こんなものをスーベニールにしたら、ご本人の審美眼が問われるだろう。
寄ってくる彼らに、もっと工夫を凝らせと叱咤したくなる。同じようなモノで競争していたら値下げ競争を自ら課しているようなものだ。自分で新商品を開拓しろ、と言いたくなる。それこそベニン王国様式で造形し、ブラックアフリカのセンスでディフォルメしてみたらと彼らの思考回路を混乱させたくなる。
しかし、考えてみれば、彼らは、かつても今も、そして未来も「観光客」として越境することはないだろう。とすれば自分を豊かな「観光客」にと立場を置き換えてみることができない。いっけんして彼らは不法滞在者、まともな職にありつけないビザなしの不法越境者、とその服装、立ち姿からそううかがえる。
『サンバ』の主人公サンバ(オマール・シー)は、そんな街頭商人のなかに混じっているようなアフリカはセネガル出身の青年だ。主演のオマールは、同じ役柄、不法越境労働者役を演じた『最強のふたり』で好演、ハリウッドへの進出もはたし上昇気流に乗っている。そのオマールが『最強のふたり』の監督と再度、タッグを組んだのが本作。今回は、人気女優シャルロット・ゲンズブールと迎え商品性もグレードアップさせての一編。
ビザをもたないサンバは空港近くに設けられている出入国管理事務所の施設に強制収監されてしまう。いまや先進諸国の都市にはどこにでも存在する施設だ。東京にもあるが顕在化しない。日本にも同じような問題があるはずだが、オーバスティの不法滞在者たちが映画に登場し、自ら自己主張することは稀れだ。けれど、フランスはもとよりEU諸国では繰り返し不法滞在者の問題がスクリーンに登場する。ハリウュド映画なら麻薬密売からみの作品のなかでは必ずメキシコやコロンビアからの越境者が登場するのが定番。不法越境者はいまの時代を写す鏡なのだ。その鏡をもたない日本映画はある意味、歪つな存在だと思う。
東京のド真ん中、トルコ大使館前でトルコ人とクルド系トルコ人の衝突があったことは、まだ記憶に新しい。中国人観光客の多さあけに目を奪われてはいけない。観光ビザで入国した中国人が多数、の不法滞在者としてどこかで不法労働しているという現実もある。日本国内にもさまざまな問題が存在するということだ。
サンバは収監された施設のなかで、かつて人材派遣会社で有能なエリートとして働いていたアリス(シャルロット・ゲンズブール)と出会う。アリスは仕事に疲れ、不眠症など合併症状を起こして現在はリハビリ中、その治癒行為として不法移民の救済活動にボランティアとして関わる。その最初の相談相手がサンバであった。
親身に、人権思想とかいった高邁な理想からではなく、すこぶる庶民的感覚の人助け精神だろう。理論武装していないだけ情にほだされるということだ。相談に乗っているうちに、いつしか、サンバの真摯な姿に魅せられ、やがて恋に落ちるというパターンは常道。そのおおらかな公道を語るうちに、サンバを通してみえてくるヨーロッパ諸国の不法移民問題が日常光景として映像化される。それも『最強のふたり』と同じ構図だ。
こうした作品を見ていると、パリで瞥見した街頭スーベニール商の男たちにもそれぞれ過酷な越境の旅譜があるのだろうと思う。
移民たちはより稼ぎのよい経済力のある国に流れる。シリア難民たちはドイツへ入りたがった。ドイツではその流入を巡って政権を揺るがす問題が生じた。英国のEU離脱問題の大きなファクターはそうした移民の流入問題があった。
サンバの友人となる自称ブラジル人ウィルソンが、やがてサンバからアラブ系のイスラム教徒であることが暴かれる。ウィルソンはブラジルからの越境者であることを自称することによって、フランスに根強くある反イスラム感情を避けようとしているのだ。そんな人間模様が描かれてゆく。
こみ入った語りの複雑さはないストレートな作品だから分かりやすい。英国で移民問題をたびたび映画化しているケン・ローチ監督流の社会批評の鋭さ、過敏さは希薄。ベクトルがまったく違うところで制作されている。善い悪いでいうのではなく、さまざまな描き方があるということだ。日本では、その手法論を語れないほど作品事例が少ないということだ。これは単純に日本映画の社会性の稀薄さを意味する。 2016-09記
映画の地球 これから公開 自ら解毒する性根のない作品 アルゼンチン映画『笑う故郷』 ガストン・ドゥブラット監督
自ら解毒する性根のない作品 アルゼンチン映画『笑う故郷』 ガストン・ドゥブラット監督
