映画の地球 プーチン独裁したのロシア映画 5 t.A.T.uのポップスをBGMにしたチェチェン紛争映画『厳戒武装指令
t.A.T.uのポップスをBGMにしたチェチェン紛争映画『厳戒武装指令』ニコライ・スタンブラ監督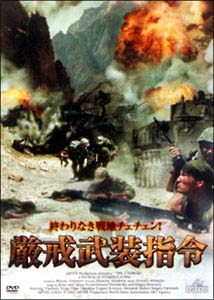 冷戦末期、ソ連はアフガニスタンに介入して混迷し、共産党独裁の崩壊に繋がった。
冷戦末期、ソ連はアフガニスタンに介入して混迷し、共産党独裁の崩壊に繋がった。
アフガニスタンの親ソ派政権を維持するための武力介入は、ソ連を疲弊させた。
タタール人の侵入、ナポレオンのモスクワ占領、ナチ・ドイツ軍の侵攻に対する戦いは基本的に平原での戦いであった。勇猛果敢なコサック兵も平原での騎馬戦に長けていた。しかし、アフガンでの戦いは、険しい山岳地帯の地勢をよくしるゲリラ戦のなかで苦闘した。
ソ連軍には山岳地帯での戦いに対する教典はあっただろうが、実戦から学ぶことは少なかった。ソ連圏を大戦後、ほどなく離脱したチトー大統領のユーゴスラビアにソ連が介入できなかったのも、地上戦では山岳戦に長けたチトー軍との戦いをい避けたからだ。
アフガンの戦いでソ連軍は確かに学んだ。多くの若い兵士たちが血と肉を飛散させて山岳戦の要諦を学んだのだ。代償はあまりにも大きかった。甚大な兵士の死は、やがてソ連そのものを崩壊させたのだ。
いま、中央アジア諸国の墓地を訪れると、アフガン戦争で戦死した若い兵士たちの墓標が林立しているのをみることができる。彼らの墓標を確かめるために訪問したわけではないが、中央アジア諸国に散在する大きな墓地にはたいてい日本将兵の共同墓地があり、その墓参に訪問すると、そこに若い青年像を墓碑に複写した墓が林立して目につくのだ。
日本将兵の墓とはいうまでもなくシベリア抑留時代の強制労働で亡くなった無念・無慚と望郷の涙のなかで病み、あるいは飢えのなかで死んでいった人たちの墓である。近くへいけば、それに手を合わせるのは日本人の義務と思う。
一度、ウズベキスタンの首都タシケント郊外の墓地で、日本の墓参ツアーに出会ったことがある。先日、安倍首相が詣でた墓地だ。
その墓地には日本将兵とおなじように抑留生活で命を落としたドイツ軍将兵の墓がある。アフガン戦争で命を落とした若い兵士の墓もある。けれど、ドイツ軍将兵の墓に目を留める日本人はいないし、また阿部首相も気がつかなかっただろう。ましてやアフガン戦争で戦死した若者の墓など一顧だにされない。そういう安倍首相の姿、日本人墓参団の行動を地元のひとたちは注意深くみていることを忘れてはならない。
中央アジアのイスラム国から多くの若者がアフガンの戦場に狩り出された。戦場まで近いということ、同じような風土に生活していること、そしてアフガンのタジク語に通じている者が多いことも理由だった。
しかし、ハリウッドがベトナム戦争の矛盾、非人道性を早くから映画化したようにはソ連のモスクワとレニングラード(現在サクトス・ペテルブルグ)の二大撮影所はアフガンの負け戦を撮らなかった。
共産党独裁下ではいうまでもなく表現の自由は封殺され、負け戦さを描くなどもってのほか、という時代だった。映画人は沈黙していた。それがソ連映画界だった。
しかし、チェチェン戦争では早くから映画が撮られた。政府に批判的な視点からも撮られている。
アフガン戦争のように封印するのではなく、チェチェン独立過激派のテロを描くことによって、戦争の正当性を訴えられるとおもっているのかも知れない。前に取り上げた『大統領のカウントダウン』などは、その典型だろう。
〈チェチェン〉はロシア映画に繰り返し描かれることになる。ベトナムが米国人の最大の関心事になったように、〈チェチェン〉はロシアの安全・平和を語る際のキーワードになったからだ。
ソ連時代、欧米はもとより日本でも〈チェチェン〉を知るものはなかったが、ソ連崩壊後、にわかにロシアでもっとも有名は自治共和国として浮上した。その内戦の苛烈で・・・。
だから、〈チェチェン〉を記号としてロシア映画を観ていくとプーチン政権下での表現の自由、検閲の許容度が理解できる。あるいは、チェチェンに対する政策の変化、あるいは連邦内の少数民族に対する政策の変容もなんとなくわかってくる。
チェチェンの戦場では、かつてアフガンで戦友だったロシア人とチェチェン人が死闘を交えるということになった。そんなエピソードが語られるのが本作である映画に(2002*原題「前進 突撃」 )があった。日本では劇場未公開ままでVHS、そしてDVDでの発売となったため知る人が少なし、まともな批評は日本で書かれなかった。一部、戦争映画おたくがB級アクション扱いで紹介していたぐらいだろう。この映画はまず、プーチンが第2代ロシア大統領に就任して3年目に入った時期に制作されている。
ロシア軍に徴兵され空挺部隊に志願した孤児院出身の主人公サーシャのチェチェンでの戦いが縦軸として流れ、そのあいだに幾つかの挿話が挟み込まれ、ロシア現代史の歪みが垣間見えるという仕掛けだ。サーシャの戦争という視点からだけみればB級戦争アクションとなるが、むしろ、挿話のほうが興味深いのだ。
たとえば、映画にアフガンの戦地で同じ釜の飯を食った旧ソ連軍兵士がいま、チェチェンの戦場で敵対しているという現実がある。ソ連軍がアフガンから完全撤退を完了したのが1989年。その5年後には第一次チェチェン紛争がはじまっている。ソ連崩壊直後、エリツィン大統領の時代だ。若き兵士時代、アフガンで戦友だった男たちが、数年後にチェチェンで敵同士となるのはきつい現実だろうし、それは悲劇だ。実際にそんなことはあったはずだ。
映画はチェチェン人の武装勢力を決して唾棄すべき存在としては描いていない。むしろ、チェチェンの混乱に乗じて入ってきた外国籍のイスラム過激派組織の存在を指弾している。
また、サーシャの戦友ウラジミールがチェチェン武装勢力に捕獲された後、脱走中の戦闘で戦死するのだが、その父親が息子の安否を案じて、ふと過去を振り返るシーンがある。
「チェコスロヴァキアの動乱を国は、社会主義を崩壊させようとする帝国主義の陰謀だと教えられ、チェコ人を武力弾圧した。しかし、それはチェコの民主化運動を潰したことだったことを後で知った」と。
それを聞かされるウラジミールの妹は、「チェコではそんなことがあったの」と世代間の位相が象徴される。
海外に出てゆく映画で、ロシアがチェコでの“犯罪”を認めた例は少なくとも筆者にははじめて知る。
チェチェンでの戦闘を描きながら、ウラジミールの妹、その友人たちが享受する青春は、t.A.T.uのポップスをBGMにして描かれる。それもまたロシアの現実であった。